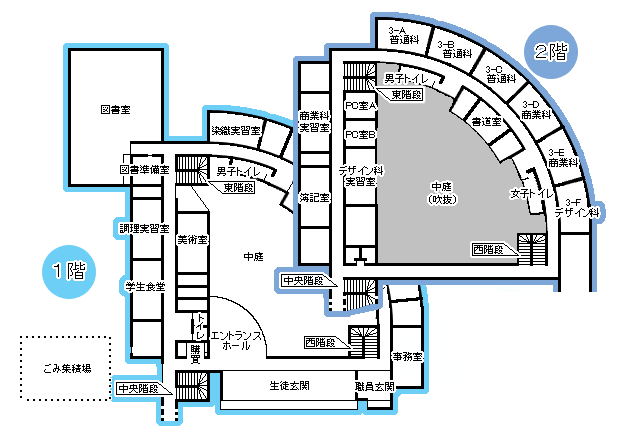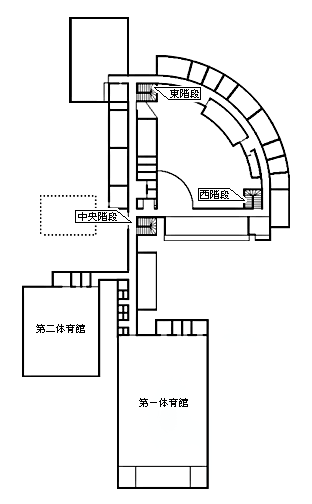ネバーランドの子どもたち 05
囁きを交わすようなさあああ、という雨の音は一晩中止むことなく続き、
目覚めた翌朝・カーテンを開ける前からその日も雨であることは予想がついた。
窓の外に広がるまだ見慣れぬ風景は案の定薄暗い中に湿ってたたずみ、
陰鬱そうに押し黙っているようにの目に映る。
ニュースの気象情報は今日も全国的に雨が降り続く一日、と予告していた。
昨夜のうちに洗濯を済ませて乾燥機に放り込み、
しっかりアイロンまでかけ終えておいた制服をひとつひとつ取り上げ、
なんだか今日も気乗りがしないなあと思いながらそれらを身に付ける。
オーダした制服がいつ出来上がってくるかは知れたものではない。
望ましくない目立ち方をしてしまうことはその間は仕方がないかもしれないが、
ありったけ勇気を振り絞って、今日こそは同じクラスの女の子と知り合わなくちゃと、は胸のうちで決心した。
昨夜の残りのシチューとトーストの朝食を摂りながらちらちらとテレビを気にしてもみたが、
市内で男子高校生が行方不明になったというニュースの続報は流れなかった。
もしかすると、例の“ネバーランドの子どもたち”の件とは関係がないのかもしれない。
しかし昨夜ニュースでそれを知ったときは、なんらかが符合したように思われてならなかった。
過去にもあったという失踪事件と、今また起こり始めたという失踪事件。
ふたつの事件をつなぐ、“ネバーランドの子どもたち”という謎めいたキーワード。
何の記憶も持ち合わせないと、何かを知っているらしい六人の幼なじみたち。
危険だと言った彼らの言葉の示すところを、は推し量ることもできずにいる。
のろのろと朝食を終えて身支度を整え、は浮かない顔で家を出た。
雨は今日も容赦なく傘の布地を打つ。
昨日の登校時に道に迷ったことを教訓として今日はさらに早い時間に家を出てみたが、
実際に歩いてみると下校のときに六人に囲まれるようにして帰ってきた道をなんとかたどることができそうだった。
頼りない歩調でしばらく行くとコンクリートで幅を固められた川が道に沿い始め、
“天野川”と書かれた青い看板が見えた。
昨日の登校時にはこの川を見た覚えがない、ということは、ここに至る以前には道を違えて歩いていたのだろう。
自分でも呆れて息をついてしまう。
川に垂直に交わる格好の道路がそのままコンクリートの橋として川面を横切っており、
さびの目立つ橋の欄干には行書体で“しらさぎばし”と名前が刻まれたプレートがはめ込まれている。
はきょろきょろと視線を巡らせながらその橋を渡った。
昨日の下校時に川沿いの道を逆に来て橋を渡ったのを、うっすらと覚えている。
二日続けて雨が降り続いたためなのか、泥混じりの色をした川の流れる勢いは激しく、
巻き込まれたらしい木の枝や空き缶などが時折、虚しげにくるくると渦巻く水に飲み込まれていった。
歩く速度にあわせて移り変わりゆく視界に特別な感慨など何もわいてはこず、
は川面を横目に見下ろしながら橋を渡った。
この町は、やはりにとってはよく見知った場所ではない……のだ。
「あ! おおい、ー!」
ふいに後ろから大声で呼ばれ、は何事かと振り返った。
駆け寄ってきたのは善法寺伊作である。
昨日も見かけたビニル傘をさし、重そうなかばんに身体を傾けながら走ってくる。
「おはよう! 今日は迷わないで来られたみたいだね」
伊作はにっこりと笑った。
おはよう、善法寺くんと答えると、伊作は困ったように微笑んだ。
「なんだか聞き慣れなくてむず痒いなあ、その呼び名……」
「えーと……なんて呼んだら?」
「あ、いや、の呼びやすいふうで構わないんだけど、ぜんぜん。
昔はいさくん、て呼ばれてたよ、僕は」
「……今もそれでいいのかな……」
「そのほうが僕は居心地いいけど、多分皆もね」
並んで歩き出しながら、伊作は他愛のないおしゃべりと呼べるだけの話題で通学路を彩ってくれた。
伊作の自宅はの自宅と同じ茜町内にあって家が近いのだという。
通学路も大半同じルートを辿るとあって、学校への行き帰りはきっとよく一緒になるねと彼は嬉しそうに笑った。
学校が近づいたのか、同じ制服を着た生徒がずいぶん目に付くようになる。
ひとりだけ浮いた格好の自分がやはり少し居場所のないように思われて、は隠れるように傘の柄を傾けた。
「……そういえば」
伊作が声をひそめて囁いた。
「昨日、ニュースとか……見た? ローカルの」
伊作の言うところが例の男子高校生の行方不明事件をさしているのだとは、明確な主語が示されなくてもすぐにわかった。
は言葉なく、頷いた。
「……ただの家出とかだったらいいんだけど。日の出町って、わりと西高も近いしさ」
「そうなんだ……」
昨日生徒会室で聞いた事件の話の中に、西高、という単語が出てきたことを思い出す。
がぽつりと呟いたのに頷いて、伊作もそれきり、押し黙った。
雨の音ばかりが耳朶を打つ。
やがて挨拶を交わす生徒たちの声がまばらに聞こえ始める頃、
目を上げた先にはやっと校門が見えて、
この大雨の中を生徒指導にあたっているらしい文次郎と仙蔵が立っている。
よく見れば傍らには長次と留三郎とがいて、留三郎はこのどしゃぶりのなかをどうしたものか自転車でやってきたらしく、
右の手に傘、左の手では自転車の片ハンドルを支えている。
四人はと伊作の姿に気づくと各々合図のように手を上げたり目元で笑ったりした。
その姿を認めただけではなんだかほっとしてしまう。
「なんだ伊作、迎えに行ったのか?」
「よかったな、これで道はもう覚えただろう」
挨拶もそこそこに仙蔵と文次郎とがたたみかけるように続けた。
二人に苦笑いを返しながらも、の視線は留三郎の自転車へ吸い付いた。
留三郎も気がついて苦笑する。
「ああ・これ? 家出たときは小雨だったから」
乗ってきてみたはいいが、途中で雨足が強くなってしまったと彼は言った。
伊作が同情するように頷いた。
「留ん家ちょっと遠いもんね」
「チャリないと厳しいんだよな」
なんでもないことのようにさらりと答えると、駐輪場へ停めてくるからと留三郎は校門から離れた。
少しばかり呆気にとられながらも、はその背を見送った。
その耳元に長次の低い声が届く。
「もう予鈴が鳴る」
「ああ、お前たちはもう行ったほうがいい。
我々は本鈴のあとまでここにいなければならないが」
「今朝は小平太を取り締まらんとな……」
文次郎と仙蔵はハア、とあからさまなため息をついて見せた。
小平太はたまに時間ぎりぎりになって登校することがあるそうで、
生徒玄関を施錠する事務員の小松田とセーフだアウトだときりなく言い合うことがあるらしい。
「まったく今日のような土砂降りの日に限って」
「普段はむしろはやばやと登校してくるほうなんだがな……」
「まあ面白いかもしれないがな。
小平太の登校風景はなかなかアクロバティックだからな」
言って仙蔵はくつくつと笑い、文次郎は何が面白いんだと横目で軽く仙蔵をにらんだ。
ふたりと別れると、は長次と伊作に連れられるようにして生徒玄関へ入った。
長次に聞いてB組の下駄箱に空きを探し、玄関から教室へ向かう最短の道筋を教わりながら歩く。
学舎は比較的新しいものに思われたが、数年前に現在地に移転したためだという。
学校自体は創立以後数十年程度の歴史を持っており、
移転前の旧校舎はその年月をしのばせるような木造の体育館が特徴のひとつだったそうだが、
現在はその旧校舎も木造体育館も取り壊されて更地になっている。
新校舎の一部は採光の効率に配慮して扇形に設計されており、
真上から見ると“ピザ四分の一枚”といったかたちの一般教室棟を囲むように
第一・第二のふたつの体育館、特別教室棟が並んでいる。
一般教室棟は四階建てで、最上階に一年生、三階に二年生、二階に三年生の教室が位置し、
一階には職業学科が利用する特別教室や会議室、学園長室などが配置されている。
生徒玄関からの所属する三年B組の教室にたどり着くまでには、
エントランス・ホール、昼休みには小平太の天下になりかわるという購買、
調理実習室、想像していた以上に小規模な学生食堂、中庭をなど右に左に眺めながら歩き、
二階までぐるりと階段をのぼる。
B組の教室は扇形校舎の“ピザの耳”にあたる曲線部分の、“切り口”側から数えて二番目の位置にあった。
廊下が湾曲しているため曲線部分の逆の反対端に位置する教室はB組付近からは見えないが、
長次と伊作の説明によればクラスは全部で六クラスあり、
普通科がABCの三クラス、職業学科がDEFの三クラスという分類になっているという。
普通科三年生は進路別にクラスが編成されており、それは昨日あちこちで聞いたとおりだ。
また昼休みにねと言い残して伊作がC組の教室に入り、
長次に目線で促されては恐る恐るといったふうでB組の教室へ踏み入った。
先に登校していたクラスメイトの視線が一瞬鋭くに集まる。
は緊張してびくりと肩をこわばらせた。
ほんの数秒後、長次に不思議そうに見下ろされた頃には、
先ほど集まったはずの注目は不自然なほどほうぼうへ散っていて、誰もと目を合わせようとはしてくれなかった。
わざわざ避けられているような気がして、は居心地悪く身をすくめる。
昨日は結局昼休みの数分しか教室にいることができず、
は自分に与えられた座席も知らないままだった。
長次がここだと示してくれたのは窓際から数えて二列目・前後どちらから数えても四列目の席だった。
それが長次自身の席と隣り合った席で、なにかあったら彼を頼るようにという担任の意図がありありと読めた。
窓際の自席にかばんを置くと、長次は無言で中央列の後ろの席を指差した。
「あそこが小平太」
「まだ来ないね」
示された無人の机を見ながらが言うと、長次は窓の外へ視線を巡らせた。
教室の窓は学校の敷地の外側を向いていて校門が直接見えるわけではなかったが、
無理やり覗き込むようにするとかろうじて門扉が目にとまる。
長次に倣っても窓際から覗き込んだちょうどそのとき、予鈴が鳴った。
もう校門周囲にはほとんど生徒の姿はない。
生徒指導も早めに引き揚げ始めるらしく、門扉がガラガラと閉められていくのが見える。
小平太はこれで遅刻かとが思ったとき、横で長次がむ、と唸るような声をあげた。
「来た」
「え」
「間に合うかどうか」
長次の言う間に、校門の正面の道を猛スピードで走ってくるビニル傘が見えた。
傘と猛スピードのおかげで顔は見えないが、
布地を骨組みに留めるビスがはじけ飛んでいびつな七角形を描いているその傘は
確かに昨日小平太がさしていたそれと同じものに思われた。
あ、とが声をあげると同時に本鈴が鳴り始める。
すでに閉められた校門めがけて小平太は全速力で突進して来、
ぽーんと軽々、門扉に手をついてそれを飛び越えた。
「うわ……!」
着地の瞬間は建物の陰になって見えず、
本鈴の鳴り終わったそのときにはは小平太の“アクロバティックな登校風景”に
ぽかんとしているばかりであった。
「たぶん間に合ったな」
長次がぼそりと呟く。
やがて階段も二段飛ばしほどで駆け上がってきたのだろう、
勢い込んで教室に飛び込んできた小平太は傘の意味なくやや濡れた姿であったが、
長次とと目が合うとにかっと笑ってブイサインを寄越した。
隣で長次がふ、と小さく息をつく。
どうやらこれも日常の光景らしい。
がぎこちなく手を振り返してやると、小平太の後ろに現れた担当教員が早く入りなさいと呆れた声で促した。
教員は小平太が席についたのを見届けてからへ視線をくれ、
そういえば、と改めて転校生の紹介を行ってくれた。
挨拶を請われては緊張気味に立ち上がり、かたい声でどうにか自己紹介をしたが、
その間も集まってくるクラスメイトたちの物言いたげな視線は
ちくちくと肌に刺さってひどく居心地が悪く感じられた。
よろしくお願いしますと言い終わるなりはすとんと座り込み、椅子の上に縮こまった。
仲良くね、と言い置くと、担当教員は自身も小林ですと名乗り、生徒の出席をとり始める。
クラスメイトたちの名前と顔とをどうにか一致させるべく、
は出席をとるあいだじゅう教室のなかを目立たぬように横目で・ひっきりなしに眺め回していた。
恐らくひとクラスに四十人ほどが在籍しているのだろうが、
進路別のクラス編成ということで多少の人数差があるのだろう。
出席番号は男女別になっているようだった。
の知る長次と小平太とは“なかざいけ”と“ななまつ”という苗字で出席番号が前後しており、
ほとんど聞き取れない長次の返事と朝っぱらからやたら明るい小平太の返事とが立て続いた。
の苗字は“”だが、中途編入のため五十音に関係なく出席番号はいちばん最後になるらしい。
呼ばれて返事をし、やっとまともにホーム・ルームが始まってからははたと気がついた。
昨日この教室にいた数分の間にも少し引っかかっていたことではあるが、妙に女子生徒の姿が少ないのである。
昼休みの喧騒のなかではそれがたまたまそう見えたのだと言われても納得できるが、
こうして全員が着席している今見てみると
明らかにクラスの半数以上が男子生徒で占められていることがわかる。
ホーム・ルームの終わったあと、寄ってきた小平太と長次とにはひそひそと問うた。
「ね……なんでこんなに女子が少ないの? 進路別編成のせい?」
小平太と長次は一瞬相談するように目を見合わせた。
「もともと私らの学年は男子のほうが多かったんだ」
「女子生徒の志望者は例年それほど多くない」
「なんで!?」
二人はまた目を見合わせた。
小平太がアッサリとした口調で切り出す。
「ここの、大川学園高校は、もともと専修っていうの? の、学校なわけ。
職業学科があるのはその名残。
で、普通科が増える前は男子校だったんだよ。もう十何年とか、昔の話だけど」
「普通科が導入されてからはそのクラスの数が徐々に増えて、職業学科は逆にその分減ったらしい。
今は二学科・三クラスを残すのみだ」
は負けじと反論を試みる。
「で、でも、今は共学でしょ? 男子校だったのなんて、ずっと昔なんでしょ?」
「普通科導入と同時に共学校になったが……男子高校というイメージがかなり根強く残っていたようだ。
素行の悪い生徒の多い時期が長く続き、いろいろな意味で……有名だったと聞く」
「私ら子どもの頃もここの制服着てる兄ちゃんって恐いイメージあったし」
「その頃はとっくに共学でしょ!?」
「うん、でも恐かった、髪茶色で長かったし、ピアスしてたし。
あとはー……秋津台高校のせいとか?
校則もなにもユルッユルの私立校だったんだけど、
ここんとこ先生方もPTAも力入れてるらしくて、少しずつ志望者増えてるって」
「大川と同じくらいのランクだったものが二・三上がり……風紀も含めて校風がかなり改良されたそうだ。
こちらも移転して校舎が新しくなったので職業学科のための設備が整えられたりはしたが」
「職業学科もあんま女子受けする感じじゃないし、移転したあとはちょっと駅から遠くなったしね。
あと、秋津台は何年か前に制服のデザインが変わったのもあるかも」
かわるがわるに説明をしながら長次も小平太も、がどんどん気落ちしていくのがわかったらしい。
ふたりがフォローの言葉を編み出す前に、はがっくりと項垂れたままため息をついた。
「……今日こそは女子と知り合わなきゃって思ってたのに……」
「声かけりゃいーじゃん?」
「難しいよ……」
はちらりと視線を教室のただなかへ投げた。
数の少ない女子生徒はその中ですでに数人ずつの仲の良いグループに分かれていて、
転校初日から奇妙な目立ち方をしているを遠巻きに眺めて噂しているようだ。
そこに割り込んでいく勇気を今朝振り絞ったばかりのはずが、
やはり現状を目の当たりにしてしまうと萎えてしまわざるを得ない。
「だいじょーぶ、そのうち慣れるって。私らもいるし」
小平太があっけらかんとそう言ってくれるのだが、
彼らに囲まれているからこそ自身に近寄りがたい感が生まれてもいるようにも思われてならない。
転校してきたばかりの女子生徒がいきなり何人もの男子生徒に囲まれて構われている光景は、
きっと見ていてあまり気分のいいものではない。
それももちろん彼らのせいというわけではないので、は素直にその心遣いに礼を言う。
しかし、しばらく黙っていた長次がふいに口を開いた。
「……意外に深刻な問題かもしれん」
大げさにも思われる言いように、はぎょっとして長次を見やる。
「今日の四限目は体育だ」
もちろん、男女別の授業である。
長次も小平太も、そこまでの面倒を見るわけにはいかない。
めまいが起きた気がした──はもう言葉もなかった。
「体育は普通科三クラス合同だから、ちょっと女子の数も増えるよ」
「昔の知り合いの一人くらいはいるかもしれん」
慰めるようなことを二人は言ってくれるが、あまり期待できる気はしなかった。
昔の知り合いがいるかもしれないとは言っても、
この町のことをほぼまったくといってよいほど覚えていないである。
幼なじみ六人のことも記憶から抜けているほどなのだから、
相手が女の子の友達であってもわからない可能性が高いように思われた。
「あー……先が思いやられる」
は頭痛をこらえるようにこめかみを押さえた。
追い討ちをかけるかとどめを刺すかのようなタイミングで、授業開始のチャイムが鳴った。
一時間目の現代文、二時間目の世界史、三時間目の数学と教室での授業が続いたが、
にとっては散々なこと続きであった。
まずわかったのは、
授業で使う教科書がすべて転校前に使っていたものと一致しないということである。
長次に頼んで横から見せてもらいながら授業を受けたものの、
大半の教科はの習っていたところよりも少し先へ進んでいたり
まったく違う教材を履修していたりして、話はさっぱりわからない。
聞けば、夏休み前の学期末テストがもう目前に迫っているとのことで、
ある程度の成績を残そうと思うのならは必死になって追いつかねばならない。
大学受験の計画も改めて練り直さなければならないには
なにもかもが闇の中での手探り状態といえた。
進路が決定していないいまの時点で塾に行こうだとか家庭教師を雇おうだとかいう発想も具体的にはできず、
また母子家庭となったいまはあらゆるものにそうそう金をかけてもいられず。
教えてくれる相手があればいいが、友人をつくるのにもひとまず夏休みに入るまでがひと区切り、という期限がある。
(そういえば……)
昨日の帰りに、文次郎は学年トップの常連だという話を聞いたことを思い出す。
いざとなったらやはり彼らに頼るしか今のにはすべがなさそうだが、
受験勉強に真面目に取り組むべきこの時期にあまり自分のことで彼らの手を煩わせるわけにはいかない。
どうにかして自分で頑張るよりほかにないのは当然のこととはいえ、
なんだか妙なプレッシャーを感じてしまってはひやりといやな汗をかく。
三時間目の終わるチャイムが鳴ったとき、開放感に満ちた教室の中ではひとり、緊張して身をかたくした。
三クラス合同の体育の授業とあって、廊下がいきなり騒がしくなる。
B組の教室に、伊作と留三郎が顔を出した。
よろよろと近づいてきたに、伊作が気遣わしげに問うた。
「、そういえば体操着とかあるの?」
「あー、昨日保健室で借りたのをそのまままた借りちゃおうかと思って……」
「そっか、うん、それは構わないと思うけど。
……B組の女子、もう全員先に行っちゃったんだ」
「雨だからな、授業の内容変わるんだろ。
更衣室の場所もそれで変わるから、早めに移動しとくんだよ」
俺らはそこらへんでも着替えられるけど、と留三郎が廊下に視線を巡らせつつ言った。
ほとんどの生徒はもう移動し始めていて、先ほど騒がしかった廊下は今すでに静まり始めている。
A組から出てきた文次郎と仙蔵は、一目見て現状を把握したらしい。
体育館までは一緒に行くかとため息をついた。
はお世話になりますと項垂れるよりほかにない。
一階まで降りてから体育館へ続く渡り廊下を歩いていくと、少し先に“中央階段”と案内板の下がった階段が見えた。
校舎の構造から察するに、恐らく階段は全部で三箇所。
扇形をした一般教室棟の“ピザの耳”曲線部分の、A組がわの端に一箇所。
これが朝にたちが通った階段である。
その反対端のF組がわに一箇所、そして目の前の“中央階段”は名称からしてもその中間に位置する階段に違いない。
その中央階段から、一人の女子生徒が姿を見せる。
廊下を先に行く彼女はその手に体操着が入っていると思われる大きな巾着を下げていた。
あ、と留三郎が声をあげた。
「高槻!」
呼ばれて、女子生徒は振り返った。
長いまっすぐな黒髪が、その振り返る仕草にさらりと揺れる。
理知的な印象の目元は一瞬近寄りがたいような雰囲気を醸しているが、美人と呼んでいいだろう。
彼女はわずかに首を傾げ、留三郎を見上げた。
「なあに? 食満くん」
「悪い、体育さ、こいつ連れてってほしいんだけど」
留三郎は傍らのを示した。
いきなり話題の矛先が自分に向いて、はびくっと居住まいを正す。
高槻と呼ばれた女子生徒は、眉をひそめてを見据えた。
「……今朝話していた転校生ね」
「あ……です」
はまだびくびくしながら会釈して見せる。
女子生徒はにこりともせずに目礼を寄越した。
「高槻透子です。
今日は予定を変更して第二体育館でバレーボールをするそうよ」
「あー、いいなあ、バレー」
「七松くんのいるチームには誰も勝てるわけがないわ」
冷ややかに透子は返し、に向き直った。
「行きましょう。体操着はある?」
「あ、うん、一応」
「それなら問題ないわ」
透子はさっさと身を翻した。
は慌ててそれに従い、見送る六人を振り返ると手を振った。
に手を振り返しながら、留三郎が声を張り上げる。
「じゃあな、高槻、そいつ頼むな! 助かった」
肩越しに視線を返した透子に、留三郎はにかっと笑ってみせる。
留三郎にはきりっと涼しげな表情を多く見るとは思っていたが、
満面に笑ったときにはその感じがまったく和らいで消えてしまうことが内心やや意外だった。
親しみやすく頼りがいがある、という感じだ。
透子は微笑むともそうでないともつかないほどわずかに唇を引いて、ええ、と小さく答えた。
間近でそれを見て、はあれ、と少し不思議に印象を抱く。
六人のほうを振り返れば、彼らはもう第一体育館のほうへ歩き出していたが、
小平太以外の皆が何か言いたげに留三郎を見やっているのに、留三郎自身はそれに気がつく様子がない。
(ありゃ……そうなんだ)
初めて知り合えた女の子の抱く秘密──もっとも、小平太と留三郎本人以外は知っているようだ──を、
は転校早々一緒に抱えてしまったらしい。
(気づかないなんて罪な男だなー……高槻さん、結構美人なのに)
は一歩先を歩く透子を、唐突に膨れ上がった親しみをもって見つめた。
留三郎を含めた誰一人のことも覚えていられなかっただが、
今のにとっていちばん親しいといえる彼らを誰かが好いているらしいと知ると、
なにやら自分のことのように嬉しかった。
透子の案内を受けては無事に更衣室にたどり着き、体育の授業を受けることができた。
馴染めたとはお世辞にも言いがたかったものの、
同じチームになったクラスメイトとも少しばかり会話もできて、
授業の開始前よりもははるかに落ち着いてバレーボールに参加することができた。
時期はずれの転校生という要素は誰にとっても興味の大きい事柄であるらしく、
を見てひそひそと何か言葉を交わしている女子生徒もまだ少なくはなかった。
もともと身体を動かすのが好きだったは
試合の最中はすっかりそんなことも気にせずにボールを追いつづけ、
いい汗かいたと気分よく授業終了のチャイムを聞いた。
参加したミニ・ゲームは全戦全勝である。
転がっていたバレーボールをふたつ・みっつと拾い上げて用具室へ戻そうと立ち上がると、
ふいにうしろからさん、と呼び止められる。
クラスがどこなのかはわからないが、数人の女子生徒がを囲んだ。
「すごかったね、バレー得意なんだ」
「全勝だったね」
やっと打ち解けるきっかけを得られたようで、は安堵した。
口々に浴びせられる賞賛はしかし、言いたいことを遠まわしにしているように浮いて聞こえ、
は笑って答えながらも内心にじわりと訝しい思いを抱いてしまう。
ごく何気なさそうに話題の矛先が幼なじみたち六人に向いたとき、
彼女らがに声をかけた目的、話題の本題がそこにあったことはすぐにわかってしまった。
彼らが学校内でも目立つ集団であることはこれで裏付けられたようなものだが、
彼女らがを親しい友人の輪に入れてくれようとしたわけではなかったということに
少しばかり失望してしまったことは否定できない。
「どうやってあんなに仲良くなったの?」
「ぜんぜん女子と接点ないんだよ、全員」
「なのにさんにはみんな自分から構っていくでしょ」
女子生徒たちが前のめり気味に聞いてくるのに一歩後ずさりつつ、は当り障りなく答える。
「うん……昔から知り合いだから」
その“知り合い”という言葉にどの程度の親しみが内包されているのかまでは答えてやらなかった。
まるで腹の探りあいだなとは思う。
女子生徒たちは焦れて矢継ぎ早に質問を浴びせた。
「彼女とか好きな子とかいないのかな」
「ちょっと変わってるとこもあるけどみんな人気なんだよね」
「立花くんは?」
「善法寺くんは?」
答える隙もないほど次々と問われて、は困ってたじろいだ。
助けを求めるように視線を彷徨わせたとき、ふいに、話題に割って入るように涼やかな声がを呼んだ。
「さん。まだ着替えていなかったの?」
声のしたほうに皆が振り返る。
すでにセーラー服に着替えた透子が立っていた。
「あ、……高槻さん」
「身体を冷やすわよ……大活躍だったものね。
それに、きっと彼らが痺れを切らして待っているわ、早く行ってあげなくては」
透子は体育館の出口のほうに視線をやった。
さすがにこちらまで入ってこようとは彼らもしないのだろうが、
廊下の前あたりで遭遇するような気は確かにする。
透子はまたたちのほうへ向き直った。
「あなたたちも……さんが困っているでしょう。
彼らについて知りたいなら、人に頼らず自分で声をかけたほうがいいのじゃないかしら?」
誰も反論もできないでいるのを横目に、透子はさっさと体育館から出て行った。
ややあって、女子生徒たちのあいだに不満が飛ぶ。
「なあに、あれ」
「自分だって食満くんのこと気にしてるくせにね」
「ちょっと美人だからって」
それを聞いて、ああ、どこにいても女の子って同じだなあとは少しばかり辟易とする。
女の子同士のあいだにしばしばできあがるこの奇妙な絆は、の苦手とするところだった。
どこへ行くにも何をするにも一緒、部活選びにも付き合いがある、
昼食は机を並べていつもの顔ぶれで、移動教室も全員横並びで廊下を歩き、
トイレに行くときまで“皆様お誘い合わせのうえ”ときたものだ。
ある程度までは仲良しのみんなと一緒、で理解はできる。
しかしそれと同じように、誰かを仲間はずれにするときもみんなと一緒、なのだ。
この不文律、それを乱すものへの容赦のない差別は、はどうしても好きになれなかった。
それよりは、周囲に対してどこか孤立した感はあるものの、
状況を察して助け舟を出してくれたであろう高槻透子の肩をもってやりたかった。
気を取り直して質問攻めに戻ろうとした女子生徒たちを、はさえぎった。
「ごめんね、私も本当は知らないことのほうが多いから、自分で聞いて。
見た目ほど怖くないよ、全員。じゃあ」
はバレーボールを用具室にしまいにさっと身を翻す。
きっと背後では先ほど透子に向けられたような不満が、今度は自分に向けられているのだろうなと思う。
それでもはそれが怖くはなかった。
女の子の友達もできるかもしれない。
接し方は少し不器用かもしれないが、透子がを思いやってくれたことがいまいちばんの内に響いていた。
彼女が留三郎について抱いている想いについても、もう少し親しくなれば聞けるのかもしれない。
協力できたらなどとお節介を焼くつもりでいるわけではないが、身近で起きた恋の話を気にしないというのも難しい話だ。
バレーボールを用具室に戻し、更衣室へ着替えに入ったときには、もう体育館には誰一人も残っていなかった。
(高槻さんも帰りは先に行っちゃったもんね……)
質問責めをしてきた彼女らが、さえぎられて気分を害し・先に去ってしまったのはまあいいのだが、
透子には頼み込んで待っていてもらえばよかったかなとは肩をすくめる。
そのときふと、視界に違和感を覚える。
借りた体操着を入れてきた紙袋が、どういうわけか棚から床に落ちている。
ははっとして、かためて置いてある自分の手荷物に駆け寄った。
貴重品は無事だった。
臙脂色の長財布、携帯電話、鍵の束。
ただひとつ、そこから忽然と……制服一式が消えていた。
「嘘ぉぉ!?」
はその場に残っていたものをすべてひっくり返してみた。
しかし、あれば目にとまらないはずがないあの目立つ制服はやはりどこにも見当たらない。
先程が突き放した女子生徒たちの姿が脳裏をかすめる。
確証はなかったが、ほかに具体的に思い当たる相手もなかった。
「あー……だからいやなんだって、女の子のこういうの……!」
もう、と息巻くと、は紙袋に荷物をばさばさ、突っ込んだ。
ずんずん力任せに歩いて体育館を出ると案の定、
遅い遅いと一部はいらいらしながら、それでも六人全員がうろうろとの戻りを待っていた。
小平太はすでに購買で一戦交えたあとらしく、戦利品のコロッケパンをいくつも抱えている。
彼らのに対するこの振る舞いはやはり、傍目に過保護に見えていることだろう。
透子に彼らが待っているだろうと言い当てられたのも、
彼らが自分からに構いに行くと言われたことも、ちっとも不思議ではない。
「? どうした、遅かったな」
仙蔵が訝しげに眉根を寄せた。
女子生徒の話題に名前が挙がるだけある、
恐らく純粋に“格好いいから”などという理由で人気を得ているのは仙蔵なのだろう。
いつも一緒に行動しているらしい文次郎がややとっつきにくい雰囲気であることも、
逆に仙蔵の印象を和らげるのに一役かっているに違いない。
まるで告げ口をするようで、はあまり事情を話したいと思えなかった。
透子を含めた女子生徒たちは皆、彼らがを構いたがっていると現状を解釈していた。
の困窮した状況を聞けば彼らがほうぼう手を尽くして探そうとすることも、
このような嫌がらせに踏み切った相手を敵視することも目に見えている。
が緊張した面持ちで押し黙っているのを、しかし彼らは不審がった。
何も言えないまま、胸の前に抱えた紙袋を、はぎゅうと抱きしめた。
「……。制服、どうした」
留三郎が静かに聞いた。
は黙って答えなかった。
その沈黙を、彼らは正しく理解してしまった。
「ったく、陰湿だな、女どもは」
「なんでこうなった、。なにか諍いがあったか」
文次郎は呆れ果てたように言い捨て、仙蔵も腹立たしそうにそう問うた。
は黙って首を横に振る。
長次が諭すように言った。
「。言わなければわからない」
「……いいの。誰かを悪者にしたいわけでも、犯人探ししたいわけでもない」
「でも制服探さないとさぁー。なんか心当たりないの?」
「今日は体操着でもいい。そのうち、新しい制服も、できてくるし」
「よくないって」
小平太も不満げにそう言った。
また彼らにかばわれるようにしてその場にありながら、腹立たしいやら、悔しいやら、やるせないやら、
ごちゃ混ぜになった思いがのどのあたりにつかえて息苦しい。
はらわたが煮え繰り返るとはきっとこういうことなのだ。
言葉にもならない感情がぐっと煮詰まって、じわりと目尻に涙が浮かぶ。
この程度のことで泣いてたまるかと、は必死で唇を噛み締めた。
「……とにかく、探さないとな」
そう言って歩き出そうとする留三郎と、それに続こうとする一同を、は止めた。
「待って……大丈夫だから」
「大丈夫じゃないって!
体操着貸し出しておくのは構わないけど……そういう問題じゃないでしょ!」
伊作はオロオロ半分、怒り口調でに食ってかかる。
「いいの、みんなは何もしないで。……私、自分ひとりで、探すから」
立ち尽くす彼らを掻き分け、はぎこちなく歩き出した。
制服の行方を知っている者には心当たりがあるとは言っても、
直接聞いてすぐに答えてもらえるわけではないだろうし、
はぐらかされた果てに関係がさらにこじれる可能性もある。
広い校内をしらみつぶしに探すのは一人では到底無理だろう。
それでもはできることなら彼らに助けを借りずにすべて済ませたかった。
何が原因でこの騒動が起きているかといえば、
学園内でも人気者らしい六人に新参者のがお姫様よろしくちやほや構われていることへの小さな嫉妬なのである。
彼らの手を借りるのは難しいことではない、しかしそれではきっと、
いまは小さな芽ともいえる程度の嫉妬心をあおって育てることにつながってしまう。
それを思うと彼らに助けを求めることはには気が重かった。
、と彼らがまた呼ぶ。
は振り返り、少し無理をして微笑んだ。
「大丈夫。昼休み終わっちゃうし、先に生徒会室にいて。
制服見つけたら私も行くから」
彼らがそれ以上なにか言い出す前に、は踵を返して走り出した。
前 閉 次*